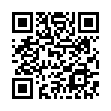会社にかかる主な税金には、国税である「法人税」、地方税である「法人住民税」「法人事業税」などがあります。いずれも会社の利益に対して課せられる税金になります。
実際の税金の計算などの納税実務について、会社にかかる税金の種類やそれがどのように計算されるかなどの基本的な部分については前もって理解しておきましょう。
・ 法人税(国税)
会社の利益に対する代表的な税金。法人税の計算の基礎となる利益は、決算で求められた最終的な利益である「税引前当期純利益」になります。ただし、この利益に単純に税率を乗じて算出されるわけではありません。
決算書上の利益に調整を行なってから、求められる「法人所得」金額をもとに算出されます。
会計上の利益は収益から費用を差し引いて求められますが、法人所得は「益金」から「損金」を差し引いて求められます。
益金は会計上の収益、損金は会計上の費用に似たようなものになります。たとえば交際費は会計上では全額費用として計上されますが、法人税を計算する際には一定の金額しか損金として認められないといった違いがあります。法人税を計算するには、この費用・収益と損金・益金の違いを調整する必要があります。
法人税額は、こうして求められた所得に税率をかけて算出します。税率は原則30%となります。ただし資本金が1億円以下の中小法人の場合には、所得が800万円以下の部分については18%の税率が適用されます。
たとえば資本金1000万円の会社で、税務調整後の法人所得が900万円の場合には、800万円×18%の144万円に、100万円×30%の30万円を足した174万円の法人税がかかることになります。
・法人住民税(地方税)
法人住民税は、会社の事業所のある自治体に対して支払う税金。
都道府県民税と市町村民税があります。東京23区に事業所のある会社については、市町村民税に当たる特別区民税と都民税を一括して納付します。
法人住民税は、資本金の額や従業員の数に応じて税額が決まる「均等割」、その年の法人税額をもとに計算する「法人税割」に分かれます。このため、所得がない場合でも、標準的には都道府県民税の均等割額2万円、市町村民税の5万円の計7万円程度は、最低限、毎年納めることになります(税率や均等割額は各自治体によって異なる)。
・法人事業税(地方税)
法人事業税は都道府県に納める税金。
所得に応じて課せられます。適用される税率は所得金額に応じて3種類に区分されており、所得金額が400万円以下の部分は5%、400万円超800万円以下の部分は7・3%、800万円超の部分は9・6%となります。
例えば、税務調整後の法人所得が先ほどの例と同じように900万円あった場合には、400万円×5%の20万円、400万円×7・3%の29万2000円、100万円×9・6%の9万6000円、を合計した58万8000円の法人事業税がかかることになります。この他、資本金1億円超の会社には、外形標準課税があります。
なお、法人住民税同様、法人事業税も自治体ごとに税率が異なるので注意してください。